たっぷりの水にトルコ石の色素を混ぜて、透明なセロファンにぶちまけて裏から覗き込んだ。そんな青だった。海の色よりも一辺倒だけど明るくて、自国の国旗よりも淡く広くて。邪魔するもののひとつもない一面のブルー。油断して視線を外したら、突然ドスンと落ちてきそうな、少しだけ重たげな色。
彼女の国の夏空は、そんな色をしていた。
「…………暑い」
照りつける陽に音があるならば、きっと今頃ジリジリと焦げるように鳴っているだろう。以前、彼女の祖国から借りた小説の一文が頭に浮かぶ。そして、追い立てられるように消えた。
ジリジリ、ジジジ。体中の水分が蒸発する悲鳴に混じって、極東の島国が夏を謳う。ジジジ。チリンリーン。平淡なようで強弱のついた虫の音。涼やかでしょう、と彼女が言った硝子の声。確かに不思議と熱を奪っていく音だけれど、それだけでは足りないくらい、彼の中は熱湯で溢れていた。息を吸って吐くだけで、汗が肌に浮かぶ。体中の体液に今、温度計を近づけたらどうなるかな。縁側と言うらしい庭先に腰掛け、軒を支える柱に寄りかかったイヴァンは、眩しさに眼を細めて重々しく息を吐き出した。
「……生きてますか?」
「暑くて融けそうだけど、なんとかね」
「それなら大丈夫そうですね。国も人も融けたりしませんから」
「……君って、だんだん本田くんに似てきたよね」
低く発せられたイヴァンの言葉には答えず、瞼だけそっと伏せて口端で笑うと、は携えた盆を置いてイヴァンの隣に腰を下ろした。カラン。どこからともなく、水気を帯びた硬質な音が鳴った。探るような瞳のイヴァンに、は透けた小麦色の注がれたグラスを差し出した。
「どうぞ」
「うわぁ、ありがとう」
「本当にイヴァンさんが融けてしまったら、困りますからね」
両手で手渡されたグラスを、両手で受け取る。細めのグラスの表面は、すでにしっとりと汗をかいていて、包み込んだ手のひらに吸い付いた。そこから伝わるささやかな冷気をたっぷりと奪い取って、ほうと息をつく。カラン。耳に届く音が、普段よりも大きく聴こえるのは気のせいだろうか。チリーン。身体の内側で穏やかな涼しさを育む響きの中で、イヴァンはグラスを唇に寄せ傾けた。
「……おいしー」
「よっぽど暑かったんですね、イヴァンさん」
「もっちろん。本田くんのところは、あったかくていいけど、暑すぎるのは辛いなぁ」
「まあ、確かに今年はとくに暑いですから。イヴァンさんや、北方のみなさんには厳しいかもしれません」
「寒いのは平気なんだけどねー」
言い終えるとともにもう一口。それから、熱気の籠もった息を吐き出すと、不思議と体中の熱が下がった気がした。この一時の冷却も、グラスの中身を飲み干してしまったら終わってしまうのかな。すでに半分以上減った手の中をみて、寂しさが募る。
ほんの数十分過ごしただけの自分でもこうなのに、毎日こんなに暑くて、この国の人たちは大丈夫なんだろうか。本当に融けたりなんかしないだろうけれど、ふと気になってイヴァンは右隣に目を向けた。
イヴァンからこぶし二つ分ほどの場所で、は庭に足を投げ出すように座っている。ショートパンツから伸びた素足や剥き出しの二の腕は涼しげだが、よくよく見れば皮膚にうっすら汗が滲んでいるのが見て取れた。そういえば、以前会議であったとき、こんなに顎が細かっただろうか。顔色も、もっと自然な赤みを帯びていて、熟れた桃のように色づいてはいなかったか。こんな、雪のような色ではなくて――――
「…きみは、融けたりしないよね」
「先ほどのまだ気にしてるんですか?私もさすがにそこまで人間離れはしていないつもりなんですけど」
「うーん。そういう意味じゃないんだけどなぁ。でもきみは、いつ消えちゃうかわからないんだよね」
「だからといって、氷や雪みたいにあっという間に消えてなくなってしまう、なんてことはないですから」
ましてや暑さでなんて…と呆れ顔では自分の分の冷水を口に流し込んだ。嚥下した喉が上下する。コクリ。彼女の音につられるように、イヴァンもグラスに残ったそれを一気に飲み干した。それから、もう一度ゆっくりと、彼女の言葉を飲み込んだ。
数ヶ月前よりも確実にか細くなった身体の線。色が失われて痩けた頬。熱いため息。
もしも人が本当に熱で融けてしまうとしたら、逆のことも可能なんだろうか。この国でトロリとした黒と白の液体になったの元を、一滴残さないように気をつけてビンに注いで、蓋をして。真冬のモスクワでそれを叩き割ったら、またそこで、は産まれるのだろうか。きっとの原液は、雪みたいに真っ白で、黒炭みたいに真っ黒なんだろうとイヴァンは思う。雑ざりあったふたつは決して相容れずに波紋のような芸術を生むだろう。指を浸したら、表面は火傷するくらい熱くて、中間層は凍傷になるくらいに冷たくて。一番奥に辿りついたら、きっとの本当の体温が待っている。そんな、気がした。
「…僕は、君なら雪みたいに暑さで融けちゃうことも、あるような気がするよ」
空になったグラスを木目が浮き出た盆に戻した途端、カラカラと氷が沈む音が手のひらに伝わった。それに気付かないふりをして、イヴァンはグラスを放した手のひらを最短距離でに伸ばした。まだ湿ったままのイヴァンの人差し指が、の頬にふれる。とどく距離に不思議と、イヴァンの口元がほころんだことに、だけが気付いていた。
頬に窪みができるほど深く押し付けた人差し指をひいて、首だけを回しての瞳がイヴァンにとどく。ごくり。上下する喉にイヴァンは今度こそ倖せそうに自ら微笑った。親指と人差し指でつまんだの頬は、やわらかくて、少しだけかわいていて、そして、あたたかかった。
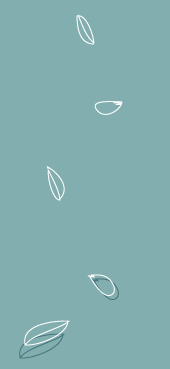
( とかして、かためて、君にふれて )